アーバンデータチャレンジ(UDC)2025の中間シンポジウムを10月25日(土)、埼玉県さいたま市浦和区にある埼玉会館 3C会議室で実施しました。
昨年UDC2024にて活動で最も優れた地域拠点に送られる「ベスト地域拠点賞」を「埼玉拠点」が受賞されたことに伴い、今年度のUDC中間シンポジウムは埼玉県で開催されることとなり、「データを活用した市民参加型の防災・まちづくり」をテーマとして開催しました。

さいたま市 情報統括監 小泉浩之 氏
今回の開催地であり、ご後援いただいたさいたま市を代表し、情報統括監の小泉浩之氏にご挨拶いただきました。
小泉氏は、さいたま市が推進する「防災アプリ」や「オープンデータポータル」など、行政におけるデータ活用の取組を紹介。
避難所の開設状況や混雑度をリアルタイムで確認できる機能、AEDや給水拠点など41件の防災関連データの公開などを挙げ、市民の安全と利便性を高めるための取り組みを説明しました。
また、データを行政から発信するだけでなく、「市民が使いこなせる環境づくりが大切」と述べ、行政・企業・大学・市民が連携しながら地域防災を進める意義を語りました。

デジタル庁 国民向けサービスグループ 参事官(防災担当) 藤本幸司 氏
藤本氏は、「デジタル庁における防災DXの取組」について講演しました。
防災データを省庁横断で集約する「防災データプラットフォーム」や、自治体の導入を支援する「防災DXサービスカタログ」などの最新施策を紹介。
特に、マイナンバーカードを活用した避難所入退所のデジタル化では、手続きを従来の1/10に短縮できる成果を示し、2025年8月に創設される「災害派遣デジタル支援チーム(D-SAT)」の構想についても説明しました。
「デジタルの力で、現場の即応性を高める防災体制をつくる」と語り、会場から大きな関心が寄せられました。

さいたま市 都市計画課 松山幸司 氏/シビックテックさいたま 桑原静 氏
続いて、行政と市民の連携によるまちづくりの事例として、さいたま市 都市計画課の松山幸司氏と、シビックテックさいたまの桑原静氏が登壇しました。
松山氏は、PLATEAUデータを活用した洪水・防火リスクの3D可視化や、Minecraftを用いた子ども参加型まちづくりワークショップを紹介。
「データを通じて“未来のまち”を子どもたちと一緒に描く」取組の意義を語りました。
桑原氏からは、毎月開催しているデジタル相談室の取り組みが紹介され、「誰でも気軽に来られる場所をつくることで、デジタルが“誰かのため”の技術になる」と、地域に根ざしたシビックテックの在り方が共有されました。
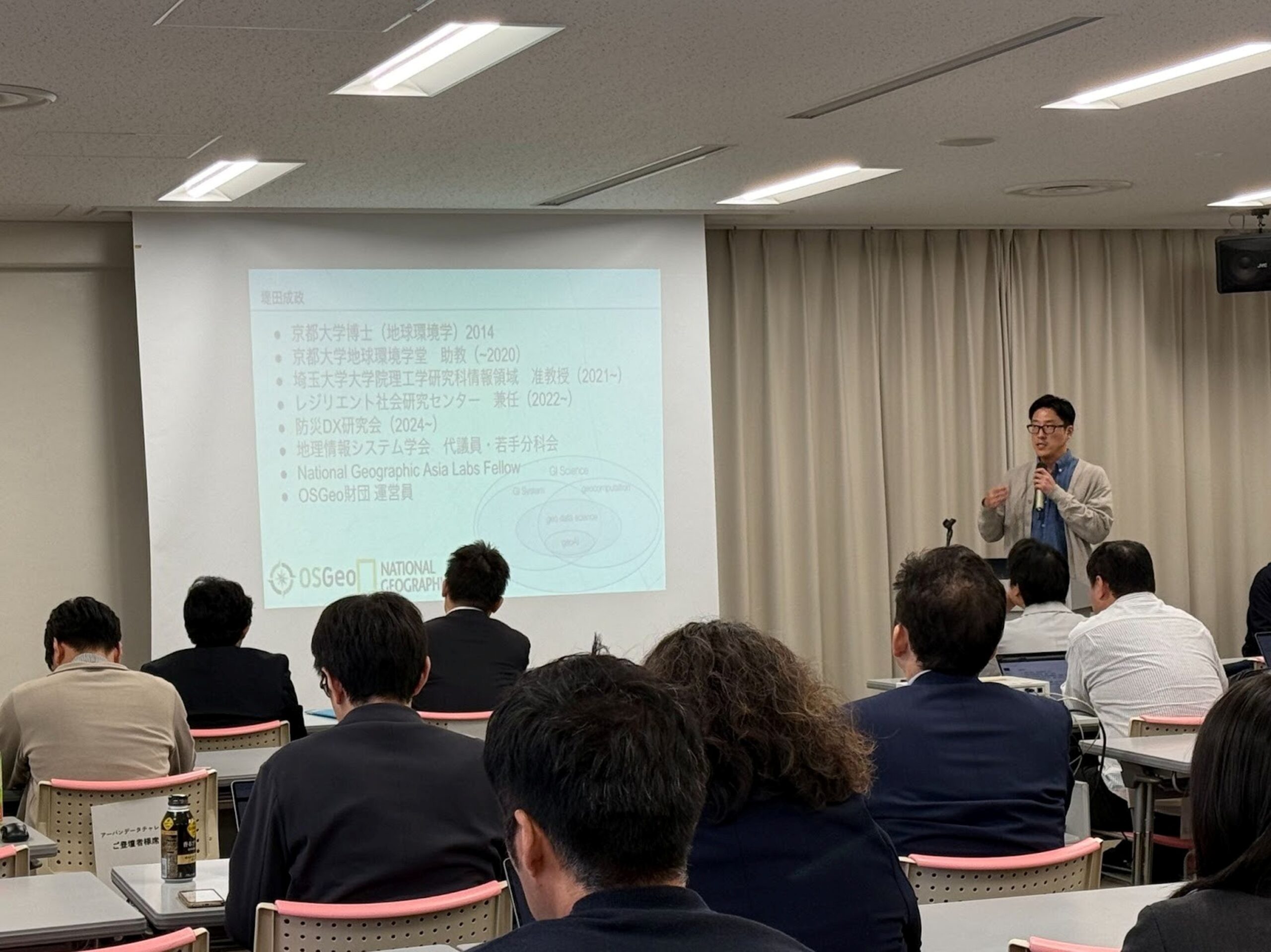
埼玉大学大学院 理工学研究科 准教授 堤田成政 氏
堤田氏は、「防災・まちづくりに向けた地理空間情報活用の可能性」と題して講演しました。衛星データとAIを組み合わせた洪水推定モデルや、建物データと人流を用いた浸水リスク評価などの研究成果を紹介。
さらに、CO₂排出量を空間的に推定する手法や、2025年7月に設立された「地域レジリエント社会研究コンソーシアム」の活動も紹介し、科学的根拠と市民協働の両輪が、持続可能な地域づくりの鍵になる」と結びました。
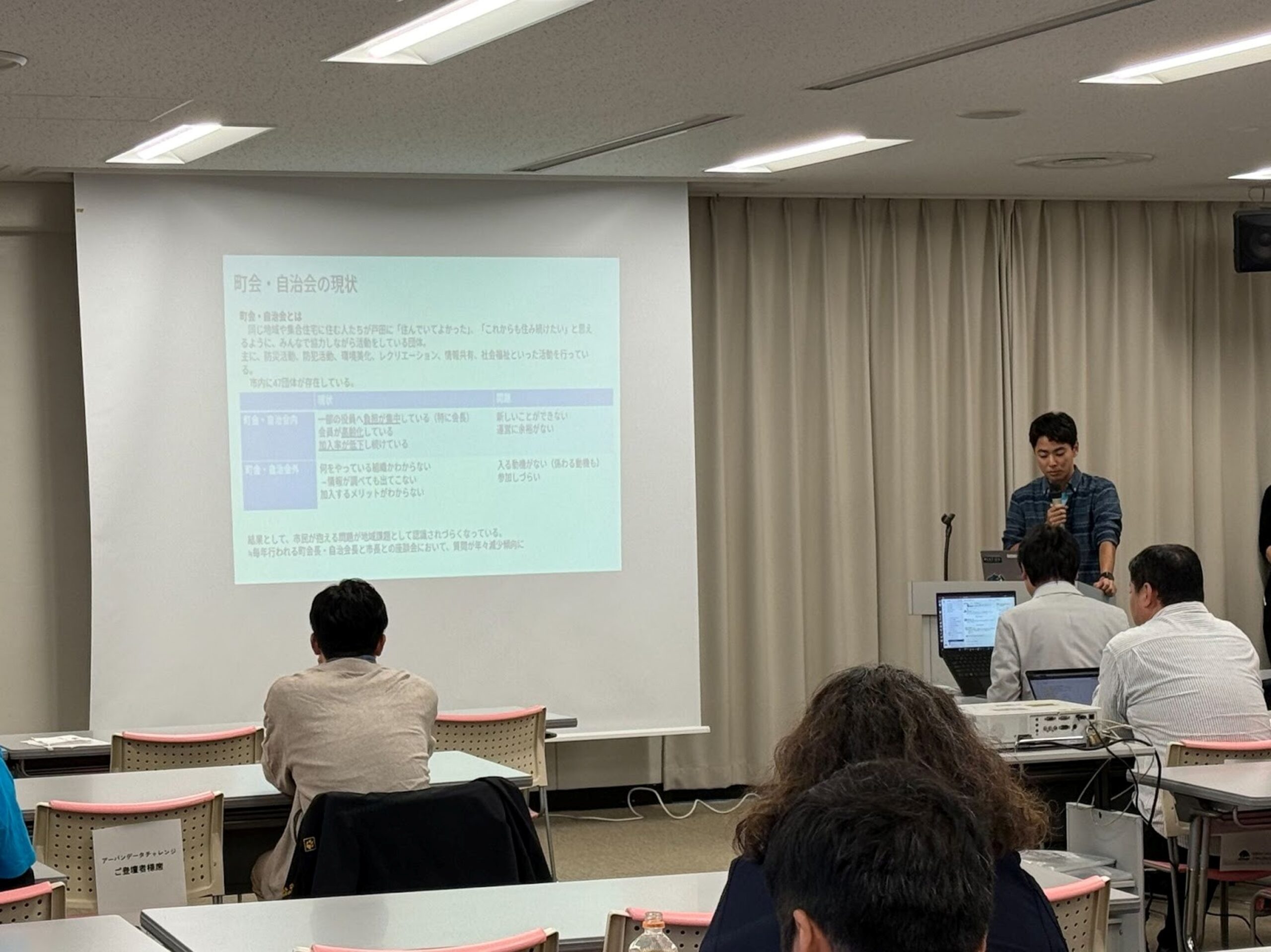
 UDC埼玉拠点(戸田市・和光市)活動報告
UDC埼玉拠点(戸田市・和光市)活動報告
第2部では、埼玉拠点から2つの市の事例が報告されました。
戸田市では、「町会・自治会のデジタル化」をテーマにしたアイデアソンを実施。
会員コミュニケーションや若年層参加を促進するアイデアを議論し、
会館Wi-Fiを活用した子どもプログラミング体験やLINE WORKS導入など、地域課題に即した実践が進められています。
和光市では、「子どもの居場所オープンデータ」をLINEで更新できる仕組みを構築。
団体がLINE上でデータを登録・更新すると、自動でオープンデータ化される仕組みにより、担当者の負担が大幅に軽減されました。今後は防災拠点や高齢者支援などへの拡張も検討されています。
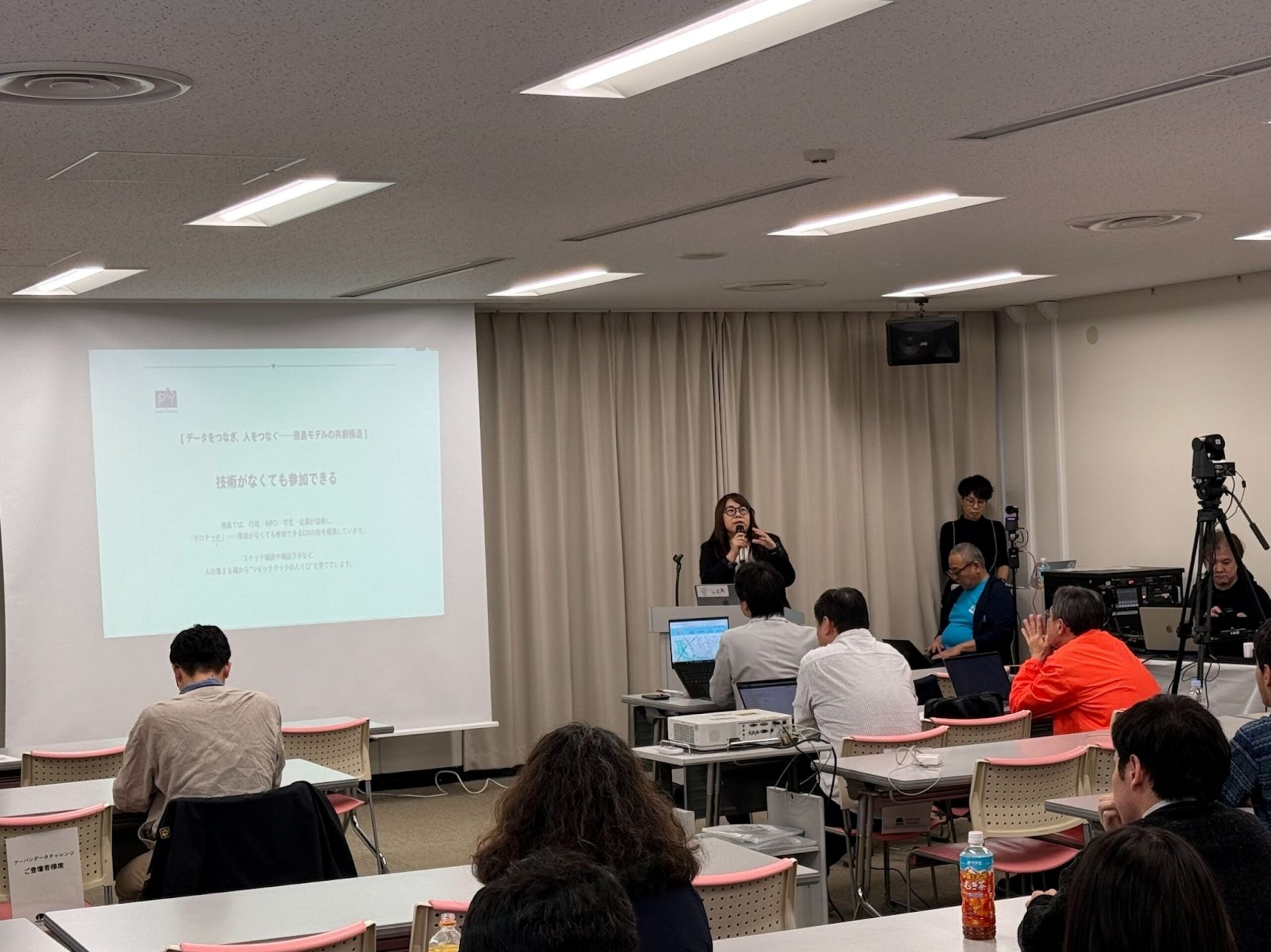
 地域拠点コーディネーターより活動報告
地域拠点コーディネーターより活動報告
徳島、静岡、宮城、佐賀の4拠点からコーディネーターが登壇し、それぞれの地域で行われているデジタルコミュニティ形成の取り組みを報告しました。拠点ごとにオープンデータ活用や市民参加の取組が紹介されました。災害対応、まちづくり、教育分野など、分野を越えた多彩な事例が共有され、地域同士の連携の重要性が改めて確認されました。
- なお、参加人数は以下の通りでした。
- 現地参加: 57名
- オンライン参加:20名
中間シンポジウムの様子を収録したアーカイブ動画は、YouTubeにて公開しております。
